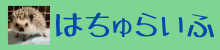爬虫類を飼ったことがない人でも飼いやすい「レオパードゲッコー (ヒョウモントカゲモドキ)」。
最近は総合ペットショップで取り扱われるケースもあり、どこかで見たことがあるという方も多いのではないでしょうか。
しかし、小動物とは飼育方法や用品、餌がまったく異なるため、爬虫類を飼ったことがない人がには馴染みがないものばかりだと思います。
そこで本記事では、初めて爬虫類を飼う人におすすめのレオパードゲッコーの飼い方を徹底解説します。
このページはこんな人におすすめ
・爬虫類を飼ってみたい
・レオパードゲッコーに興味がある
・レオパードゲッコーを飼ってみたい
スポンサーリンク
爬虫類を初めて飼う人にレオパードゲッコーをおすすめする理由
爬虫類って飼い方が特殊なイメージがありませんか?
実際に、爬虫類を飼うためには乗り越えなければいけない壁があります。
- 身体の大きくなる種類も多い
- 餌がマウスやラット、もしくは昆虫
- 太陽光の代わりに紫外線ライトが必要な種類もいる
爬虫類の中でも、レオパードゲッコーは比較的飼いやすく、爬虫類の入門種と言われることもあります。
その理由として、1番は1m〜2mにもなるモニターという種類のトカゲなどに比べ、身体が小さいことがあげられるでしょう。
レオパードゲッコーの体長は、成長しても25cm程度と小型のヤモリ。ケージは幅30cmでもギリギリ飼える大きさです。
また、ヘビや大型のトカゲの餌はマウスやラットを食べる種類も多いのですが、レオパードゲッコーはコオロギなどの昆虫が主食です。
人工餌を食べる個体であれば昆虫をあげる必要はありませんし、難しい設備も必要ありません。
例えば、昼行性という昼間に活動するタイプの爬虫類では、太陽光の代わりとなる紫外線ランプや日光浴のためのバスキングランプという保温ランプが必要になります。
一方、レオパードゲッコーは夜行性のため、紫外線ランプやバスキングランプはいりません。
更に、湿度についてもさほど厳しくない点が、他の爬虫類に比べて難しくないと言われる理由です。
- 成長しても体長が25cmくらいで、爬虫類の中では小さい
- 餌は主に昆虫だが、人工餌も販売されている
- 夜行性なので、ライト類が必要ない
レオパードゲッコーってどんな爬虫類?

英名:レオパードゲッコー
和名:ヒョウモントカゲモドキ
学名:Eublepharis macularius
爬虫類鋼 有鱗目 トカゲモドキ科
原産国:アフガニスタン・インド・パキスタン
ヤモリの仲間だが、他のヤモリと異なり瞼を持ち、指先に吸盤がないため壁に張り付くことはできない。
乾燥地帯に生息しており、夜行性で昼間は暗く湿った場所でじっとしている。
尻尾に栄養を蓄えており、太い尻尾であれば1か月は食事をしなくても生きられると言われている。多くのトカゲ・ヤモリで見られるように、身の危険を感じた時は自ら尻尾を切る「自切」を行うこともある。
元々は、その名の通り体表にヒョウモン模様を持つが、現在は品種改良により模様がないなど、様々な品種(モルフ)が作られている。
レオパードゲッコーは砂漠のような乾燥地帯で暮らしていると思われがちですが、湿度の高い場所を好む傾向があり、湿った土と岩の隙間をねぐらにしているようです。
こういった生息地域の情報は飼育環境の参考になりますので、覚えておきましょう。
レオパードゲッコーの値段
「爬虫類って高いのでは?」と思われるかもしれませんが、レオパードゲッコーは安いモルフだと4,000円くらいで購入することが出来ます。
珍しい品種(モルフ)ですと、何十万円もするようなものもありますが、一般的な品種は数千円~3万円くらいです。
人気のある品種のおおよその相場を示します。
| モルフ名 | 値段の相場 | 詳細 |
| ハイイエロー | 5,000円前後 | レオパの原種から最初に作られたとされるモルフ。黄色味が強い。 |
| マックスノー | 10,000円前後 | 黄色味を抑えたモルフ。モノクロ感が人気。 |
| スーパーマックスノー | 15,000円前後 | マックスノーより黄色味が抑えらられ、完全なモノクロになるモルフ。 |
| (ハイポ)タンジェリン | 10,000円前後 | 胴体のオレンジ色が強調されるモルフ。ハイポが入ると胴体の模様が減少する。 |
| スーパーハイポタンジェリン | 15,000円前後 | タンジェリンやハイポタンジェリンより模様が出にくい。 |
| アルビノ | 10,000円前後 | 黒色色素が減退し、胴体は黄色やオレンジ色になる。厳密には、トレンパー・ベル・レインウォーターの3種類があり、それぞれ特徴が異なる。 |
| ブラックナイト | 100,000円前後から | ブリーダーFerry氏が作出したブラック系モルフ。クオリティにより価格が大きく異なる。 |
一般的に、総合ペットショップでは価格は高めに設定されており、スタッフが飼育方法に詳しくないケースもあるため、種類の豊富な爬虫類専門店や爬虫類イベントでの購入がおすすめです。
特に、爬虫類イベントはイベント価格といって普段の設定価格より、かなりお得に購入できることがあります。
あわせて読みたい
レオパードゲッコーの飼育に必要なものと初期費用
レオパードゲッコーを飼うために必要なものはそう多くありません。
- ケージ
- シェルター(寝床)
- 保温器具
- サーモスタット
- 温湿度計
- 水入れ
- 床材
- カルシウム剤
- ピンセット
- 餌
初期費用は餌代抜きで2万円に収まるくらいです。
あわせて読みたい
レオパードゲッコーの飼育用品について詳しく知りたい
https://cap0504.com/leopard-gecko-breeding-goode/
餌の頻度と水
爬虫類は省エネな動物ですので、大人であれば毎日ご飯を食べる訳ではありません。
特に、レオパードゲッコーは尻尾に栄養をためていますので、普通体型のフルアダルト個体なら1週間〜2週間に1度でも問題ありません。
一方、ベビー(生後半年くらいまで)は毎日食べるだけあげて早く体を大きくしてあげましょう。
まだ尻尾の細いベビーの場合は、数週間食べないだけで餓死してしまう可能性があります。
生後半年から1年までのヤング個体は、しっぽがふっくらとしていれば3日に1度、細いようなら毎日あげます。
太りすぎは病気になりやすく寿命に影響することがあるため、しっぽの太さで餌の頻度を検討しましょう。
飲み水については、いつでも新鮮な水が飲めるように水入れを用意して1日1回は容器を洗って中の水を交換するようにしましょう。
カルシウム剤の添加
レオパードゲッコーの餌になる昆虫には、カルシウム剤を添加する必要があります。
カルシウム剤を餌に添加することを「ダスティング」と言います。
爬虫類用のカルシウム剤には、「カルシウム」と「カルシウム+ビタミンD3」の2種類があります。
ビタミンD3は、カルシウムの吸収を助けるビタミンの一種で、特に昼行性のトカゲやカメなど飼育に紫外線が必要な爬虫類に必須の栄養素です。
レオパードゲッコーは夜行性のため、基本的には「カルシウム」のみのカルシウム剤をメインで使用しましょう。
ビタミンD3も重要な栄養素のため、ベビーなら1週間に1回程度、アダルトなら1か月に1回程度は使っても良いかもしれません。
注意したいのは、「カルシウム+ビタミンD3」を多量に与えると、ビタミンD3の過剰摂取となり病気になる可能性があることです。
レオパードゲッコーで詳細な研究はされていないようですが、人間の場合はビタミンD3の過剰摂取で食欲不振・腎不全・不整脈などが起こることがあります。
夜行性のレオパには、普段は「カルシウム」のみのカルシウム剤を与え、ごくたまにビタミンD3入りを使うのがよいでしょう。
温度・湿度の管理
爬虫類は自分で体温を調節できないため、温度や湿度の管理は重要です。
レオパードゲッコーの最適温度は28~30℃です。
ただし、ケージ内全部をこの温度にするのではなく、一番暖かい場所が28~30℃、涼しい場所が25℃前後になるよう調整してあげましょう。
このように、ケージ内に温度の高い場所と低い場所を作ることを、「温度勾配を作る」と言います。
湿度は40~60%くらいであれば問題ありません。
日本の気候であれば、特別湿度を調整する必要はないと思います。
注意するとしたら、乾燥する冬は加湿器で湿度を上げてあげたり、脱皮する時期は60%くらいと少し高めにしてあげたりするとトラブルが少なくなるでしょう。
実際の飼育環境について詳しく知りたい
https://cap0504.com/leopardgecko-breeding/
脱皮について
レオパードゲッコーは爬虫類ですので、脱皮をします。
段々と白っぽくなり、脱皮直前は元の色はどこへやら。真っ白になります。
私の経験則ですが、白っぽいから脱皮かなと思ったら次の日には元に戻っていて、その数日後にまた白くなり脱皮することが多いように感じます。
白くなってすぐに元に戻ったら、もしかしたらまだ脱皮が終わっていないかもしれませんので、湿度は十分に保つようにしてあげてください。
50%~60%にしてあげると、脱皮が上手くいきやすいです。
上部に水を入れることのできるものシェルターであれば、管理がしやすいでしょう。
脱皮の頻度は、ベビーだと2週間とかなり早いサイクルで脱皮することがありますが、大人になると1か月〜2か月に1度くらいに落ち着きます。
レオパードゲッコーの病気
レオパードゲッコーに多い病気の代表例は、以下のとおりです。
拒食
拒食とは、なんらかの理由で餌を食べなくなってしまった状態です。
尻尾の大きい個体であれば数週間~1か月は食べずに生きられますが、尻尾の細い個体やベビーの場合は1週間拒食するだけで命の危険があります。
拒食を起こす理由として、主に以下が考えられます。
脱皮前に起こる拒食
レオパードゲッコーは脱皮前になると、餌を食べなくなる個体がいます。
体が白くなっている状態だとわかりやすいですが、まだ白くなっていないときでも餌を食べないことがあるため、見た目にはわかりにくいかもしれません。
脱皮が原因の拒食では、脱皮が終わって数日すると餌を食べ始めるようになります。
いつ脱皮したのか記録しておくと、脱皮の前後で食べなくなる期間を把握しやすくなるでしょう。
飼育温度が低い
お迎え直後や初めての冬を迎えるときなど、飼育温度が低いことで餌を食べないことがあります。
前述のとおり、レオパードゲッコーの飼育温度は28℃〜30℃程度です。
ペットショップでは30℃〜32℃程度の高温で管理されていることもあるため、お迎え前に飼育温度を確認しておくと安心です。
温度が25℃以下になると餌を食べなくなるため、ケージ内に温度計を確認しましょう。
餌が好みでないことで起こる拒食
餌が好みでない理由は、餌の種類が急に変わった場合に多く起こります。
特に、お迎えしてから食べてくれない場合は、ショップの餌と違うものをあげたため、食べないことが多々あります。
お迎え初期は、ショップで食べていたものをあげるようにしましょう。
同じコオロギでも、イエコオロギやフタホシコオロギ、クロコオロギなど種類があります。
また、餌のサイズが合わないと餌と認識しないこともありますので、その子に合ったサイズの餌をあげるようにしましょう。
目安としては、頭の半分くらいのサイズが良いとされています。
ただ、私の感覚としては半分より小さめの方が、吐き戻しや便秘を起こしにくいように感じます。
人工餌や冷凍餌をあげている場合は、活き餌に変えると食べることもありますので、試してみましょう。
活き餌の頭をとって、鼻の頭につけてあげると餌と認識しやすくなり食べてくれるかもしれません。
便秘で起こる拒食
便秘の場合は、温浴させるのが効果的です。
浅くぬるま湯をはった容器にレオパードゲッコーを入れて、お腹を温めてあげます。
便秘はケージ温度が低いと起こりやすいので、きちんとパネルヒーターが点いているか確認しましょう。
ケージ温度が28℃くらいで便秘気味なら、30℃〜32℃に上げてみるのも手です。
また、爬虫類用の整腸剤を使用することも出来ます。
下記のレプラーゼは人気の商品です。
¥963(2026/02/02 01:47:06時点 楽天市場調べ-詳細)
ヘミペニス脱
男の子の場合は、生殖器が外に出たまま戻らなくなることがあります。
綿棒などで戻す方法もありますが、自己判断せず動物病院へ連れて行ってあげましょう。
クル病
カルシウム不足により起こり、骨が変形してしまいます。
特に、成長期のカルシウム不足で起こりやすいです。
カルシウム剤をきちんと餌につけていれば起きる可能性は極めて低い病気ですので、しっかりとカルシウムを摂らせるようにしましょう。
腸閉塞
主に誤食が原因で、腸が詰まっている状態です。
非常に危険な状態ですので、すぐに動物病院へ連れていきましょう。
実は、私も経験していて、1週間ほど餌を食べないなと心配していたら、湿度対策で入れていた水苔が糞に紛れて出てきたことがありました。
誤食に全く気付かず、危ないところでしたが、自力で出してくれて、本当に良かったです。
まとめ
レオパードゲッコーは、他の爬虫類に比べて小さく、必要な飼育用品も少なくて済みます。
また、非常に温厚で爬虫類を初めて飼う人におすすめできます。
品種(モルフ)もたくさんあり、1匹飼い始めるともう1匹さらにもう1匹・・・と中毒性があるのでハマる人も多い爬虫類です。
爬虫類は難しいからと諦めず、初心者向けのレオパードゲッコーを飼ってみてはいかがでしょうか?
爬虫類を初めて飼う人にレオパードゲッコーをおすすめする理由
- 成長しても体長25cm程度と小さく、ケージは30cmからでOK
- 複数の人工餌が販売されており、昆虫を扱えなくても大丈夫
- 必要な飼育用品が比較的少なく、初期費用は2万円以下で飼うことも可能
- 動きがゆっくりで、性格が温厚
- 飼っている人が多いので飼育情報が豊富