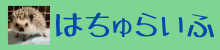レオパードゲッコーは爬虫類の入門種とも言われるとおり、初心者でも飼いやすい爬虫類です。
そうは言っても、犬や猫のような哺乳類と違って、しっかりと温度管理をしてあげなければいけません。
「でも、保温ってどうすればいいの?何が必要なの?」
初めてレオパードゲッコーを飼うとき、どんな保温器具が必要かどうやって管理してあげたら良いのかよく分かりませんよね?
このページでは、初めてレオパードゲッコーを飼う人向けに必要な保温器具や設置の仕方を詳しく解説しています。
このページはこんな人におすすめ
・初めてレオパードゲッコーを飼うので必要な飼育用品を知りたい!
・レオパードゲッコーの保温器具の設置方法がよく分からない!
なぜレオパードゲッコーを飼うときは温度管理をしないといけないの?
まず、なんでレオパードゲッコーを飼うときは温度管理が重要なのかを解説します。
変温動物のレオパードゲッコーは自分で体温調節ができない!?
レオパードゲッコーは他の爬虫類と同じように「変温動物」という括りに分類されます。
この「変温動物」とは、体温を安定して維持することが苦手な動物のことです。
人間や犬、猫、ハムスターなどは「恒温動物」と呼ばれ、食べ物からエネルギーを得て自分の力で体温を維持しています。
一方、「変温動物」は環境の温度に体温が影響を受けやすく、外気温が下がるとその影響で体温も下がりやすくなります。
環境温度が下がって体温も下がれば、活動性が落ちます。
外気温が低くなり餌になる昆虫や小動物が獲れなくなる時期は冬眠や活動性を落とすことで省エネモードに入り、餌の獲れる暖かい時期は活発になる。
よくできていると思いませんか?
レオパードゲッコーは暖かい地域の動物なので、外気温が下がっても冬眠はしません。
日本の冬のようにあまりに寒すぎると体温が下がり、餌が食べられずに死んでしまいます。
だから、レオパードゲッコーを飼うときは温度管理が必須なのです。
温度管理ができていないどうなる?
レオパードゲッコーのケージの温度管理ができておらず、ケージ内の温度低すぎると、消化不良を起こすことがあります。
レオパードゲッコーは消化不良により、便秘や吐き戻しをしてしまいます。
特にベビーでは、消化不良がそのまま命の危険につながることもあるので注意が必要です。
レオパードゲッコーに適した温度は?

レオパードゲッコーを飼うときに適した温度は、一般には25~30℃と言われています。
25~30℃って幅があって、結局何度にすればいいの?と思いますよね。
レオパードゲッコーを飼うときは、ケージの温度を低いところで25℃前後、温度が高いところで28~30℃になるように温度勾配をつけます。
レオパードゲッコーは自分で体温を調節することが苦手なので、暑いときは涼しい場所に、寒いときは暖かい場所に移動して体温調節しています。
ですので、ケージ内に25℃前後の涼しい場所と28~30℃の暖かい場所を用意してあげる必要があるという訳です。
28~30℃と書きましたが、大人のレオパードゲッコーは28℃前後、ベビーは29~30℃にしてあげると良いでしょう。
ベビーのレオパードゲッコーはまだ消化器が未熟なので、温度が低いと消化不良を起こしやすくなるからです。
レオパードゲッコーに必要な保温器具

レオパードゲッコーに必要な保温器具には大きく分けて2種類あります。
ケージ内の空気を温める保温器具とケージの床を温める保温器具です。
ここではそれぞれの役割について詳しくみていきましょう。
ケージ内の空気を温める保温器具
ケージ内の空気を温める保温器具は、前項で説明したレオパードゲッコーの適正なケージ内の温度(25~30℃)にするために使用します。
ケージ内の空気を温める保温器具にも種類があり、遠赤外線を利用した保温器具とランプを使用した保温器具、電熱線を利用した保温器具があります。
遠赤外線タイプの保温器具
遠赤外線を利用した保温器具の特徴は、保温器具の表面温度が高温になりにくく、レオパードゲッコー が誤って触れてしまっても火傷しにくい点です。
また、後述するランプや電熱線の保温器具と違って、ケージ全体を温めることができます。
本体の費用はランプや電熱線の保温器具よりも高いですが、ランプが切れることはないので1度買えば半永久的に使用できるのが利点です。
おすすめの遠赤外線を利用した保温器具は、爬虫類飼育に欠かせない「暖突」という保温器具です。
暖突は、ケージの天井に吊るすタイプの保温器具で、表面の温度が上がらないので火傷の心配もなく、耐水使用なので霧吹き程度の水では壊れません。
私もレオパードゲッコーの他にハリネズミとファンシーラットに使用するほど愛用しています。
ただし、暖突は取り付ける位置によっては温度が上がりにくく、また室温が低いと適正な温度に上がらないこともあるので、特に冬に室温が20℃以下であるようなら不向きです。
保温球タイプの保温器具
保温球を使用した保温器具は、外気温に左右されにくく、室温が低くてもケージ内を温めることができます。
ただ、電球の表面は高温になるので、レオパードゲッコーが誤って電球に触れてしまうと火傷をしてしまう危険があります。
また、レオパードゲッコーのケージは幅30cmと小さい場合も多く、保温球タイプの保温器具だと温度が上がりすぎてしまうこともあります。
さらに、電球には寿命があり、交換が必要になるためコストがかかります。
保温球タイプでおすすめはこちらの遠赤外線を利用した保温球。
レオパードゲッコーの小さいケージ内に設置することもできるくらい小型です。
保温球タイプですが、遠赤外線なので火傷しにくく、電球の寿命も長いのが特徴です。
ケージの床を温める保温器具
レオパードゲッコーには、ケージ全体を温める保温器具の他に、ケージの床を温める保温器具も必要です。
ケージの床を温める保温器具は、レオパードゲッコーのお腹を直接温める役割があります。
お腹を温めると消化が良くなり、便秘や消化不良による吐き戻しを防ぐことができます。
ケージの床を温める保温器具を一般的に「パネルヒーター」と呼び、爬虫類の飼育用品メーカーからさまざまな種類のパネルヒーターが販売されています。
基本的にはどのパネルヒーターでも大きく差はありません。
違いと言えば、パネルヒーター自体に温度調節機能がついたものがあるくらいでしょうか。
パネルヒーターはケージの床全体に敷くのではなく、ケージの床1/3~1/2に敷きます。
用意したケージに合わせたサイズを選んでくださいね。
レオパードゲッコーは小さいケージで飼うことが多いと思うので、XSサイズやSサイズなど小さいサイズも揃っているエキゾテラのパネルヒーターがおすすめです。
レオパードゲッコーの温度管理の仕方
レオパードゲッコーに必要な保温器具を用意したら、ケージにセットします。
ここでは、レオパードゲッコーの温度管理の仕方についてみていきましょう。
レオパードゲッコーの温度管理にあると便利なアイテム
前項で解説した保温器具は、任意の温度に設定することはできません。
でも、レオパードゲッコーに最適な28~30℃に設定したい!
そんなときに使うのが、「サーモスタット」です。
この「サーモスタット」を保温器具に接続すると、ケージ内の温度がサーモスタットで設定した任意の温度になると自動で保温器具の電源をオフにしてくれます。
そして、ケージ内の温度が設定温度より下がると、今度は電源をオンにして再びケージ内を温めて設定温度内に維持してくれるという優れものです。
爬虫類を飼育をしている人は、保温器具をこの「サーモスタット」に繋いで飼育温度を管理しています。
おすすめの「サーモスタット」は、コスパの良いこちら。
アクアリウム用なのですが、爬虫類にも使えます。
爬虫類用のサーモスタットは高いので、私はこれで代用していますが、特に不具合はありません。
ただし、あくまでアクアリウム用ということはお忘れなく。
爬虫類用ならこちらがおすすめ。
保温器具の設置の仕方
では、具体的にどのように保温器具を設置すれば良いのでしょうか?
レオパードゲッコーを飼うときは、温かい場所で28~30℃、涼しい場所で25℃前後になるようにしますので、基本的には下の画像に設定します。

パネルヒーターはケージの床の1/3~1/2に敷きます。
そして、サーモスタットの温度センサーは、暖突の下に取り付けましょう。
試しに1番暖かくなる場所と涼しい場所、それぞれに温度計を置いて温度の確認をしてみてください。
思った通りの温度になっていれば、温度管理はばっちりです。
また、レオパードゲッコーの寝床となるシェルターの置き場所ですが、パネルヒーターの真上には置かないようにします。
シェルター内が高温になってしまうことがあるのと、ウェットシェルターの場合はシェルター上の水がすぐに乾いてしまうことがあるからです。
パネルヒーターの上に置くなら、シェルターが半分パネルヒーターにかかる位置に置くようにしましょう。
レオパードゲッコーの温度管理 まとめ
レオパードゲッコーの温度管理の大切さと必要な保温器具、ケージレイアウトについてまとめました。
レオパードゲッコーの保温器具は暖突+パネルヒーターを選べば間違いありません。
また、温度管理用にサーモスタットも用意しましょう。
レオパードゲッコーの温度管理のキモは、ケージ内の1番温かい場所が28~30℃に涼しい場所が25℃前後になるよう温度勾配をつけることです。
レオパードゲッコーをお迎えする前に、理想の温度になっているか、実際にケージにセットして温度チェックをしてみてくださいね。
この記事もおすすめ