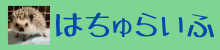水槽を立ち上げて熱帯魚飼育を始めたばかりの頃は、水槽の水質が安定せずバランスが崩れて、熱帯魚が調子を崩しやすくなります。
そんなときに活用したいのが、「水質検査」です。
水槽を立ち上げたばかりで水質が安定しない時期は、特に大事な指標になりますので水質検査の方法をしっかり理解しておきましょう。
このページでは、なぜ水質検査をするのかという基本から検査用試験紙の使い方までを解説します。
このページはこんな人におすすめ
・これから熱帯魚を飼う!
・水槽を立ち上げる時の注意点を知りたい!
・水質検査の方法を知りたい!
なぜ、水質検査をする必要があるの?
なぜ水質検査が必要なのでしょうか?
それは、熱帯魚の居心地の良い水であるかどうかを知るためです。
熱帯魚にとっての「水」は、私たちで言う「空気」のようなもの。
「空気」が汚れていたら私たちは咳が出たり、病気になってしまいますよね?
それと同じで、「水」が汚れていたり不純物があると、熱帯魚は病気になったり最悪命を落とすことになります。
その重要な「水」を管理する指標として、水質検査を行うのです。
水質検査って何を検査しているの?
そもそも水質検査って何を検査しているのでしょうか?
水質検査では、主に飼育水のpH・アンモニア・亜硝酸塩・硝酸塩・塩素を測ります。
これらの項目を測ることで、その水が熱帯魚に適したものなのかが分かるわけですね。
その他にも項目はあるのですが、水槽立ち上げ時に大事な項目だけあげさせてもらいました。
少し化学的な話で難しいので、ここではかみ砕いて分かりやすく説明します。
pH
pHとは、水溶液(ここでは水槽の水)の性質を表す単位です。
ざっくりとアルカリ性、酸性、中性などと言われることもあります。
pH ~6 :酸性
pH 7 :中性
pH 8~ :アルカリ性
おおざっぱにいうと、こんな感じです。
これなら聞いたことがありますよね?
ちなみに人の身体はpH7の中性です。(もう少し細かく言うと、pH7.3~7.4)
魚も同じで、大体pH6.5からpH7.5くらいまでが許容範囲です。
これが、極端に酸性よりだったり、アルカリよりだったりすることは、生命の危機にもなりますのでpHはとても大事な指標です。
アンモニア・亜硝酸塩・硝酸塩
ここらへんから化学のお話になるので、私のように化学アレルギーの方のためにザックリと説明しますね。
ただの水道水に有機物(餌など)を入れると、アンモニアが発生します。
このアンモニアは毒なので、アンモニアが多い水では魚は生きることが出来ません。
アンモニアを分解してくれるのが、バクテリア、つまり細菌です。
バクテリアは、発生したアンモニアを亜硝酸塩という物質に変えます。
この亜硝酸塩も、アンモニアほどではないけど毒性が強い物質です。
更にバクテリアが働くと、亜硝酸塩は硝酸塩に変えられます。
硝酸塩も毒性はあるのですが、アンモニアや亜硝酸塩ほどではなく、換水をすることで薄めることもできます。
水質検査は、アンモニア→亜硝酸塩→硝酸塩に変わる反応が起こっているかを知ることが出来るのです。
もし、アンモニアが検出される場合は、アンモニアを亜硝酸塩へと変えるバクテリアいないということになります。
また、アンモニアは0だけど、亜硝酸塩が検出される場合は、亜硝酸塩から硝酸塩へと変えるバクテリアがいない、もしくは少ない可能性があります。
バクテリアは時間が経てば増えてくるので、アンモニアや亜硝酸塩が検出されている場合は熱帯魚はまだ水槽へはいれず、アンモニアと亜硝酸塩が0になるまで待ちます。
硝酸塩だけが検出されるようになったら、熱帯魚を水槽へ入れても良い時期です。
更に、硝酸塩の検出が多くなっていたら、水換えをするタイミングだと分かります。
塩素
塩素も熱帯魚にとっては有害物質となります。
水道水は殺菌の目的で微量の塩素が含まれています。
熱帯魚を飼うときは、水にカルキ抜きを入れることはご存じだと思いますが、このカルキ抜きは塩素を抜くために使用しているのです。
つまり、水質検査で塩素を測るのは、カルキ抜きがきちんと出来ているかを確認するためです。
水質検査の種類
水質検査には、試験紙と自分で試薬を添加するキットタイプのものがあります。
【試験紙タイプの特徴】
メリット:操作が簡単・安い
デメリット:精度は高くない
【試薬添加キットの特徴】
メリット:試験紙より正確
デメリット:手間がかかる・高価
試験紙法による水質検査の手順

今回は、より簡単な試験紙タイプでの水質検査の方法をご紹介します。
試験紙部分が湿ってしまうと使い物にならなくなるため、容器内を乾燥した状態に保てるように密閉度の高い容器になっています。
使用後はきちんとフタを閉めるようにしましょう。
フタを開け、中身を取り出す

中身を取り出すと、スティック状の試験紙が入っています。
このまま使用しても良いのですが、コスト削減のため半分に切って使っている方が多いです。

切るときに注意したいのは、ハサミは綺麗かどうか。
水分が付いていると、切った時に試験紙が反応してしまうことがあり使えなくなってしまいます。
水槽の水をコップに汲んで試験紙を浸ける

水槽の水に直に浸けると、試験紙の試薬が水槽内へ入ってしまうことになるので心配です。
安全のためにも、コップなどに水槽の水を少しだけ汲んで、そこに試験紙を浸けるようにしましょう。
水に浸けるときはじっくり浸すのではなく、手元の黒い印のところまでサッと素早く浸けるようにします。
ポイント
・水に浸けた試験紙スティックは、コップの縁で水をきる
・それでも余分な水分が残ってしまったら、ティッシュでとる。

このとき、試験紙をテッシュに触れさせてはいけません。
スティックの横をテッシュに当てるだけで十分です。
こうすることで余計な水分がとれ、にじんだり、隣り合った試験紙の試薬が混ざっておかしな色になることを防ぐことが出来ます。
平らなところに置く
余分な水分を手早くとったら、平らなところに置きます。

決して斜めにしたりしてはいけませんよ。
判定
説明書に記載の通りの時間を待ったら判定です。

このときも、水平に持って色味を判定します。
今回の検査では、亜硝酸塩も硝酸塩も検出されず、pHも範囲内でした。
熱帯魚水槽の水質を検査してみよう! まとめ
この試験紙タイプの水質検査は、水につけて色を見るだけでできるので、初心者でも簡単に水質検査を行えます。
また、半分に切って使えるのでコストパフォーマンスも良いです。
半分に切ったものと、切っていないものを同じように検査してみましたが、どちらも同じ結果になりました。
半分に切ったからと言って、性能が落ちることはなさそうです。
ただし、メーカー推奨ではありませんので注意して下さいね。
試験紙タイプの水質検査で注意すべきポイントをもう一度載せておきます。
・劣化を防ぐため、使用しない時は必ずフタをする
・試験紙を水に浸けたら、すばやく余計な水分をとる
・判定までは水平に置いておく
この注意点だけ気を付ければ、誰でも簡単に水質検査を行うことが出来ます。
熱帯魚の健康のためにも、是非水質検査を行ってみて下さいね。